
JR東海は2022年3月24日、プレスリリースにて2023年度までにN700Sを40本投入すると公表した( 2022年度重点施策と関連設備投資について )。またJR東海は2022年5月27日、プレスリリースにて2023年度以降もN700Sを毎年投入し続けると公表した( 2021 年度重点施策と関連設備投資について )。今回はこれらから2024年3月実施予定の東海道新幹線ダイヤ改正のうち「のぞみ」を中心に見ていく。
静岡・小田原・豊橋に増停車あるかも?2024年3月実施予定の東海道新幹線「ひかり」ダイヤ改正予測はこちら!
1. 全車ブレーキ性能向上で最高速度引き上げか!
JR東海では2023年度までにN700Sを計40本投入するほか、既存のN700系のN700S対応改造を全て終わらせる。
対象となるのは2024年度までに実施分がJR東海N700系およびN700Aのうち86本、2026年度までに実施分がJR西日本N700系およびN700A16両編成全40本となている。この中には2007年~2011年に投入したN700系初期型からすでに2回ブレーキ力向上改造を受けた編成も存在する。また2023年度までに新型車両N700S16両編成をJR東海分42本、JR西日本4本投入するので、2024年3月ダイヤ改正時点でN700Sと同等の性能を持つ東海道山陽新幹線16両編成は172本中132本となる。
ただ、2022年5月には2023年度以降もN700Sを追加で投入するとしている。概ね毎年7本ずつ、2026年度までに19本を投入することで車両更新を図る見込みだ。これにより2026年度までに59本のN700Sを投入することとなる。
いや待て。N700Aとして投入した2013年以降の車両をN700Sと同等の改造をするのは分かるが、たった数年で置き換える車両をブレーキ性能向上改造をする必要はあるか?
普通に考えて、新幹線車両はたいてい20年しかないので(JR東海に至っては13年~15年程度で置き換えているが)、長寿命化工事を行うことはほとんどないしましてやブレーキ性能の向上なども車両更新を以て行うことが多い(N700系でも山陽・九州新幹線「みずほ」「さくら」用8両編成はブレーキ改造工事なんてしたことがない)。
しかも過去にJR東海では2004年~2006年の3年間東海道新幹線用の車両新製投入を一切していないことから、N700Aの改造だけで済むならN700Sを追加投入しようということにはならないはずだ。にもかかわらずN700Sを追加投入しするにもかかわらずN700Aのブレーキ性能向上改造をわざわざ余命数年の車両にも施すことを考えると、ブレーキ性能向上にそれなりのメリットを期待していると言わざるを得ない。
では既存のN700Aを含むN700系に対しN700S同等のブレーキ性能向上改造を行うことでどのようなメリットが生まれるのだろうか。
日本の新幹線では緊急時でも4km以内に列車を停止できるようにしている。が、停車時の追突を防ぐために4分間隔より広げて運転することが条件となっている。山陽新幹線など多くの新幹線は4kmで停車できるようにすればよいとしているのでN700系のブレーキ性能でも300km/h運転を行える。が、東海道新幹線では最短3分間隔で続行運転を行うため3km以内に列車を停止できる速度でしか運転していない。この差がN700系営業開始時に山陽新幹線では300km/h運転を行ったのに対し東海道新幹線内では270km/hしか出さなかった原因である。
この後ブレーキ性能を改良したN700Aの投入及び既存のN700系のA化改造に伴い2015年3月14日東海道新幹線ダイヤ改正で東海道新幹線の最高速度を285km/hに引き上げることに成功した。
今回のN700SでもN700Aと比べブレーキ性能が向上していること、および2015年時点のN700Aのブレーキ力と比べN700Sは10%程度ブレーキ性能が向上していることを考えると、N700Sと同等のブレーキ力があれば東海道新幹線で300km/h運転を行うことができるようになる。
もっともN700SはSiC素子活用による技術革新で編成重量をN700系と比べ軽量化しているため、N700Sの方が加減速効率が良い。JR東海では米原~京都間で330km/h運転による試運転も行っていることから、もし300km/hを超える運転をするとすればN700Sのみになるのではないだろうか。
ただ2015年3月14日東海道新幹線ダイヤ改正での最高速度引き上げ時には700系はN700A対応改造を行わず東海道新幹線内270km/h運転のまま据え置いている。そう考えると今回のN700S対応改造も2013年以前に投入したN700系については改造を敢えてしなくてもよさそうだとは思うが、営業に用いる全列車を同時に改造することによるメリットはまた記事後半で話そう。
2. 最高速度の引き上げでどのようなダイヤ改正を行うのか
まずJR東海所属車両のすべてののブレーキ改良改造が終わり東海道新幹線内での最高速度300km/hへの引き上げを反映したダイヤ改正を行う可能性が高い2024年3月東海道新幹線ダイヤ改正ではどのようなダイヤ改正を行うのだろうか。
まず2020年3月14日東海道新幹線ダイヤ改正にて全列車がN700系による運転に統一したが、以降東京~新大阪間の「のぞみ」の所要時間は早朝深夜は2時間21分~2時間24分、昼間の「のぞみ」毎時12本運転可能なパターンダイヤ時間帯は定期列車・多頻度列車・僅少列車問わず2時間27分~2時間30分となっている。
これをもし2022年現在のの最高285km/hから300km/hに引き上げるとすれば「ひかり」「こだま」の追い抜きを考慮しても早朝深夜は多くの列車で2時間18分運転を行えるほか、昼間は一律で3分の所要時間短縮が見込まれる。この一律3分所要時間短縮により早朝深夜は最速で2時間18分、昼間でも2時間24分で東京~新大阪間を到達できるようになる見込みだ。
特に早朝深夜に関しては2020年3月14日東海道新幹線ダイヤ改正の時に山陽新幹線内を含め3分繰り上げ・繰り下げに対応できるよう各列車を調整しているため問題なくできる。
この300km/h対応による一律3分の所要時間短縮で東海道新幹線では16両編成を1運用離脱させることができる可能性があるほか、東京~岡山・広島・小倉間でも所要時間を3分短縮することで航空機との競合にも影響を及ぼし得る。
2.1. 300km/h対応で3分短縮できるのか
(2023.6.17 追記)では車両側が300km/hに対応したところで、東海道新幹線で300km/h運転はできるのだろうか。
ふつうの新幹線であればカーブは半径4000m(以下、R4000カーブ)としており、300km/hまでなら車体傾斜装置なしで進行することができる。山陽新幹線はこの規格に従っているため車体傾斜装置のないN700系8両編成(「さくら」型車両)でも300km/h運転ができる。
一方世界初の高速鉄道東海道新幹線は1959年から1964年の東京オリンピックまでの間に突貫工事で作ったことから、用地取得を容易にするために原則R2500カーブにしたとしている。このR2500カーブではのちにカント量200mm、カント不足量100mmまで許容で255km/h運転が可能になったほか、N700系の車体傾斜装置使用で本則+20km/hの275km/h運転ができる。ただ今回の最高速度引き上げでは285km/hから300km/hへの引き上げとなるため、R2500カーブの通過速度は制限速度の275km/hのまま変わらないため、所要時間の短縮にはつながらない。
ただ東海道新幹線工事誌土木編(国立国会図書館デジタルコレクションで会員登録があれば日本全国から無料で閲覧可能)を見ると、実は神奈川県、静岡県静岡以西、岐阜県、滋賀県内はR2500カーブではなくR3000カーブが主体となっている。このR3000カーブではカント量180mmとしておりカント量不足を考慮すると270km/h運転が可能なほか、N700系の車体傾斜装置使用で本則+20km/hとなるならば290km/h運転が可能なはずである。2023年現在の最高速度が285km/hであることを踏まえると、R3000カーブでは速度を5km/h引き上げることができる。
しかも三河安城駅周辺や滋賀県内はそもそも線形の都合からカーブ自体が少なく、トンネルもないことから車両性能さえ合えば300km/h運転は可能だ。
これらを踏まえるとN700Sの東海道新幹線内300km/h運転開始に伴い東京~新大阪間で所要時間を短縮し最速2時間18分運転を行うことは可能そうだ。
2.2. JR西日本N700系に関しては「こだま」と2時間27分「のぞみ」でしのぎか
(2023.6.17 追記)とはいえ、2024年3月ダイヤ改正時点ではJR東海の全東海道新幹線車両が300km/h対応になるのに対し、JR西日本の16両編成は300km/h対応のN700S2本を投入するもののそのほかのN700系・N700Aは東海道新幹線内では285km/h運転しかできない。
とはいえ東海道新幹線の最高速度を270km/hから285km/hに引き上げた2015年3月14日東海道新幹線ダイヤ改正では270km/hまでしか出せない700系新幹線が残っていたほか、N700系も一部が285km/h対応が終わっていなかった。このためそもそも東海道新幹線を走る全車両が新しい最高速度に適応しなければならないということはない。
とはいえ285km/hで運転できる時刻枠の確保は必要である。ただ前節での所要時間一律3分短縮をしても285km/h運転ができるパターンダイヤの時刻スジがある。
1つは東海道新幹線「こだま」。毎時2本あり所要時間が長いので「のぞみ」より運用数が必要な列車で、285km/hから300km/hに引き上げたところで停車駅が多いのですぐブレーキをかける必要性があることから、所要時間がほとんど変わらない。このため285km/hのままで他列車に影響が出ないので構わない。
一方「ひかり」は米原停車便は東京~名古屋間で「のぞみ」に抜かれないほど速く運転しなけれなまらないし、静岡停車「ひかり」も名古屋~新大阪間で「のぞみ」とほぼ同じ時間で走らなくてはならないため、300km/h対応車である必要があるだろう。
そうなると残るは「のぞみ」となるわけだが、昼間の2時間24分運転列車は300km/h対応車両でないとできないが、2時間27分運転であれば従来の285km/h運転でも対応可能だ。
特に好条件なのが山陽直通で2023年時点で東京~新大阪間で2時間30分運転を行っている臨時「のぞみ」で、東京毎時42分発/毎時03分着、東京毎時00分発/毎時45分着の毎時2本である。そもそも車両は最大限運転できる東海道新幹線で毎時17本運転ができるほど用意しなければならないのだが、毎時4本枠のある山陽直通「のぞみ」の臨時増発自体設定日数が少ないので少ない運転日に性能の低い車両を使用するということになる。
もっともJR西日本は製造した車両を長く使いたいので(1997年に導入した500系然り)、停車駅が多かったり運転日が少ないことで年間走行キロが減り台車の摩耗を防ぐことで長寿命化を図ることはJR西日本にとってもメリットがある。果たしてJR西日本は2007年より導入したN700系16両編成をいつまで使い続けるのだろうか。
ただ、多額の費用をかけたJR東海のN700系改造工事は2024年度で終了することから、改造しても効果がないと言われればただの無駄足としか株主に思われない。いや安全性というのなら新車への採用だけで会社として十分な説明になるので従来車に行う必要性がない。効果が表れる2023年度末に性能向上を示すことを実際にしなければ株式会社としてメンツが立たない。そう考えるとJR東海は2024年3月ダイヤ改正で性能向上を示すために東海道新幹線での最高速度を引き上げざるを得ないだろう。
ただ、1つ可能性があるとすれば岡山発着「ひかり」にJR西日本N700系運用をどうしても残さざるを得ない場合、その周辺の「のぞみ」も含めて所要時間を短縮できない可能性がある(特に浜松で抜かす「のぞみ」2本と京都で抜かす「のぞみ」1本)。そうなった際にはまたダイヤ改正ごとに所要時間を短縮する列車を設定することになる。毎年ダイヤ改正による変更があるので当サイトとしてはうれしいが、会社的に頻繁に時刻変更を行うのはいかがなものかと思うが。実際に2010年以降大手私鉄で2年に1度しかダイヤ改正を行わない会社もあり、実際JR東海でも在来線はダイヤ改正を行わなかった年もあるので。
3. 最高速度引き上げと同時に「のぞみ」値上げか!
ではなぜ数年で廃車になる車両も含めブレーキを改造し全車両での最高速度引き上げを図ろうとしているのだろうか。
JR東海は2022年度は一応営業利益を確保したものの年間17億円と2019年度までと比べても遠く届かず、このご時世で収益繰りが悪くなっていると言わざるを得ない。
そこで考えられるのが東海道新幹線「のぞみ」の値上げである。
そもそも鉄道運賃及び新幹線特急料金(自由席相当額)の上限変更には国土交通省の認可が必要であり、その都度審査をされる。ただし座席指定料金およびグリーン料金は届出で構わないため、基本的に言い値で決めることができる。
ほとんどの新幹線では運賃及び新幹線特急料金(自由席相当額)上限額を運賃とし、自由席相当額に座席指定料金を加えたものを特急料金としている。
もっとも東海道新幹線では「のぞみ」と「ひかり」「こだま」で特急料金が異なるため、それぞれで新幹線特急料金上限の認可を受けているほか、乗り継ぎ時の差額も認可を受けている。この加算額の上限額は2019年10月1日消費税増税に伴う新幹線特急料金改定時において、東京~新大阪間で1,020円、東京~博多間で1,940円にて申請し認可しているのである。
ただ2022年現在東京~新大阪間では320円、東京~博多間では640円の加算額で設定しているのは、上限認可料金とは別に割安な料金を届け出ているためである。このため現行料金と上限認可料金の差額である東京~新大阪間では700円、東京~博多間では1,300円の値上げがそれぞれ届出のみで可能である。つまり東海道新幹線「のぞみ」の値上げは比較的容易にできるのだ。
これにより2024年3月東海道新幹線で最高速度引き上げを図り値上げした場合、紙のきっぷでは東京~新大阪間は通常期指定席14,720円から15,420円に4.8%値上げするほか、東京~博多間は23,390円から24,690円に5.5%値上げする見込みだ。近年の物価高騰を考えても約20年据え置いている運賃・料金を4~6%値上げするのは妥当な範疇と言わざるを得ない(少なくとも特急料金値上げと西九州新幹線開業により1年以内に3割値上げするよりはるかにマシである)。
またJR東海は子会社のJR東海ツアーズにEX旅パックを発売させエクスプレス予約と連動することで列車制限がほとんどない新幹線と宿泊がセットになった旅行商品を発売、東海道新幹線における家族旅行・個人旅行を囲い込み各旅行会社から旅客を奪っている。その補填として「のぞみ」を値上げすることで各旅行会社が手配する団体旅行で最大20%まで掛けられる旅行会社手数料も値上げできることからそこで帳尻を合わせて各旅行会社への顔向けとしている可能性も考えられる。
なおEX予約やスマートEXのうち、早得商品は値段を据え置く可能性が高いが、スマートEXサービスは紙の切符の200円引きと決まっているので紙のきっぷが値上げすればその分値上げするのは間違いないし、EX予約サービスも紙のきっぷと同額とまではいかなくてもある程度の値上げは十分考えられそうだ。
また2027年以降に開業するリニア中央新幹線の品川〜新大阪間利用時の運賃と料金の合計額は東海道新幹線「のぞみ」の1,000円増以内とするよう国土交通省から強く強く言われている。が、もし「のぞみ」自体の運賃を値上げしてしまえば、リニア中央新幹線の運賃も「のぞみ」値上げ分そのまま値上げすることができる。つまり東海道新幹線「のぞみ」の値上げは、リニア中央新幹線の運賃・料金値上げにも有用なのだ!
そして東海道新幹線「のぞみ」の値上げを図るタイミングとして一番適切なのが、東海道新幹線の300km/hへの引き上げだろう。
もし「のぞみ」の値上げを行うに当たり最高速度引き上げを条件とする場合「のぞみ」を極力全列車で最高速度引き上げを行わなくてはならないし、その際に多くの列車で所要時間短縮を図りに行くはずだ。そして東海道新幹線を運行する全ての車両がN700Sと同じブレーキ性能を持つ、つまり東海道新幹線内で300km/h運転ができるブレーキ力を持てるのが2024年3月ダイヤ改正である。
もし2024年3月ダイヤ改正での「のぞみ」料金の値上げを図っているのなであれば、2024年3月ダイヤ改正で大幅に時間短縮して料金値上げの口実とするはずなので、2023年3月ダイヤ改正も小規模に終わる可能性が高そうだ。そう考えるとN700Sの投入本数からして早朝深夜のみの所要時間短縮が可能だった2021年3月13日東海道新幹線ダイヤ改正や、東京~博多間の定期「のぞみ」毎時1本がN700S専用運用化できたはずの2022年3月12日東海道新幹線ダイヤ改正の2年連続で、小規模でパターンダイヤ時間帯以外のみのダイヤ改正にとどまったのも頷ける。
なお2019年10月1日の「のぞみ」と「ひかり」の新幹線特急料金差額である東京~新大阪間で1,020円、東京~博多間で1,940円というのは、1992年~1993年の「のぞみ」運転開始当初の「ひかり」との差額東京~新大阪間で950円、東京~博多間で1,800円を消費税3%から10%に反映した額である。もっとも現在の水準にまで「のぞみ」新幹線特急料金が値下げしたのは2003年10月1日に値引きしたからなのだが、今回の値上げを図ったとしても2024年3月東海道新幹線ダイヤ改正で「のぞみ」の料金を上限認可いっぱいまで値上げしても1992年~2003年頃の水準に戻るだけである。
4. 「のぞみ」値上げと同時に全車指定席化か!
とはいえ、「のぞみ」の指定席特急料金を値上げしても1~3号車を自由席として残し「ひかり」自由席と同額の特定特急料金で利用できるとなると、安い自由席利用が増えかねず十分な増収が見込めないほか、車掌検札も考えると効率が悪い。
ましては繁忙期では「のぞみ」指定席と自由席の差額は東京~新大阪間で1,750円、東京~博多間で2,670円にまで広がると考えると、席を指定せずに自由席を利用しようとする人は多くなりかねない。
このため2024年3月東海道新幹線ダイヤ改正と同時に「のぞみ」特急料金を値上げした場合、全車指定席に戻して自由席を廃止する可能性が高い。
とはいえ多客期も含め「のぞみ」を全車指定席にして問題はないのだろうか。
2020年3月14日東海道新幹線ダイヤ改正より実施している「のぞみ」最大毎時12本運転が可能になったことにより「のぞみ」「ひかり」「こだま」の中で「のぞみ」が一番空くようになったほか、2022年4月~5月の大型連休では、日によって東海道山陽新幹線「のぞみ」が指定席全列車満席となったが、自由席は最大混雑率80%とどの列車にも空席があったほどである。つまり「のぞみ」毎時12本ダイヤにより多客期であっても全ての旅客が着席できるようになっるほど「のぞみ」は空いているのである。
もっとも制度上満席時には「のぞみ」新幹線特急料金より530円安い立席特急券を発売するのだろうが、多客期を含め立席特急券を発売することは極めてまれとなるだろう。
またそもそも「のぞみ」は1992年3月12日の運転開始当初は全車指定席で、2003年10月1日の第二次のぞみ大増発の際に山陽新幹線内で「ひかり」の補完を行うために自由席を設けることとなった経緯があるが、その山陽新幹線を運営するJR西日本では2020年9月1日のJR神戸線特急「らくラクはりま」の全車指定席化を皮切りに、近畿地方で完結する特急列車を順次全車指定席化している。このことから直通するJR西日本でも全車指定席特急列車を拡大する機運はあるようだ。
もし2024年3月ダイヤ改正で「のぞみ」の指定席特急料金を値上げするのであれば、東京~博多間での通常期指定席と自由席の差額が2,470円にまで広がってしまい差額が開きすぎてしまう。そう考えると加算料金引き上げに伴い「のぞみ」を全車指定席化し安価な自由席を廃止にしてもおかしくはない。
さらに究極は「のぞみ」「みずほ」のJR通算運賃制度からの分離によるネット予約と「のぞみ」「みずほ」停車駅のみでの発売化だ。2022年6月25日からのエクスプレス予約の九州新幹線拡大もこの暗示の可能性もあるが、全車指定席化してしまえば理論上できなくもない。
ただ、「のぞみ」よりも停車駅の多い「ひかり」や東海道新幹線全駅停車の「こだま」は従来通り自由席を残すだろう。「ひかり」から自由席をなくしたら静岡県知事がどの剣幕で怒るかは想像に容易いし、16両中9両〜10両が自由席の「こだま」が突然全車指定席になるとも考えにくそうだ。
(2023.6.17 追記)JR東海では2023年秋にエクスプレス予約の価格アルゴリズムを変更、紙のきっぷやスマートEX同様「のぞみ」と「ひかり」「こだま」に同様の料金差を設けることとなった。おそらく「のぞみ」「みずほ」値上げ時の差額設定簡素化のためのものだろう。「のぞみ」値上げのプロセスは着実に進んでいるようだ。
5. 結び
今回の2024年3月実施予定の東海道新幹線ダイヤ改正では、東海道新幹線で最高速度を少なくとも300km/hに引き上げることにより「のぞみ」を中心に所要時間短縮を図る一方で、「のぞみ」特急料金改定及び全席指定化により値上げを図る可能性が高そうだ。
今後も東京・名古屋・大阪の三大都市圏を結ぶ交通の大動脈、東海道新幹線でどのようなダイヤ改正を行うのか、見守ってゆきたい。
川勝辞任で2025年3月こそ東海道新幹線最高速度300km/hへの引き上げがあるかも?2025年3月実施予定の東海道新幹線ダイヤ改正予測はこちら!
静岡・小田原・豊橋に増停車あるかも?2024年3月実施予定の東海道新幹線「ひかり」ダイヤ改正予測はこちら!
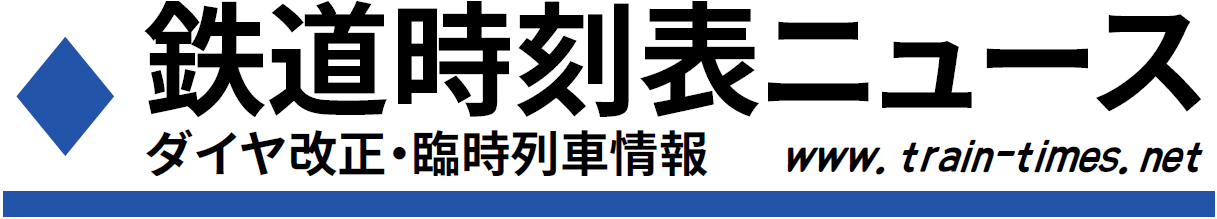






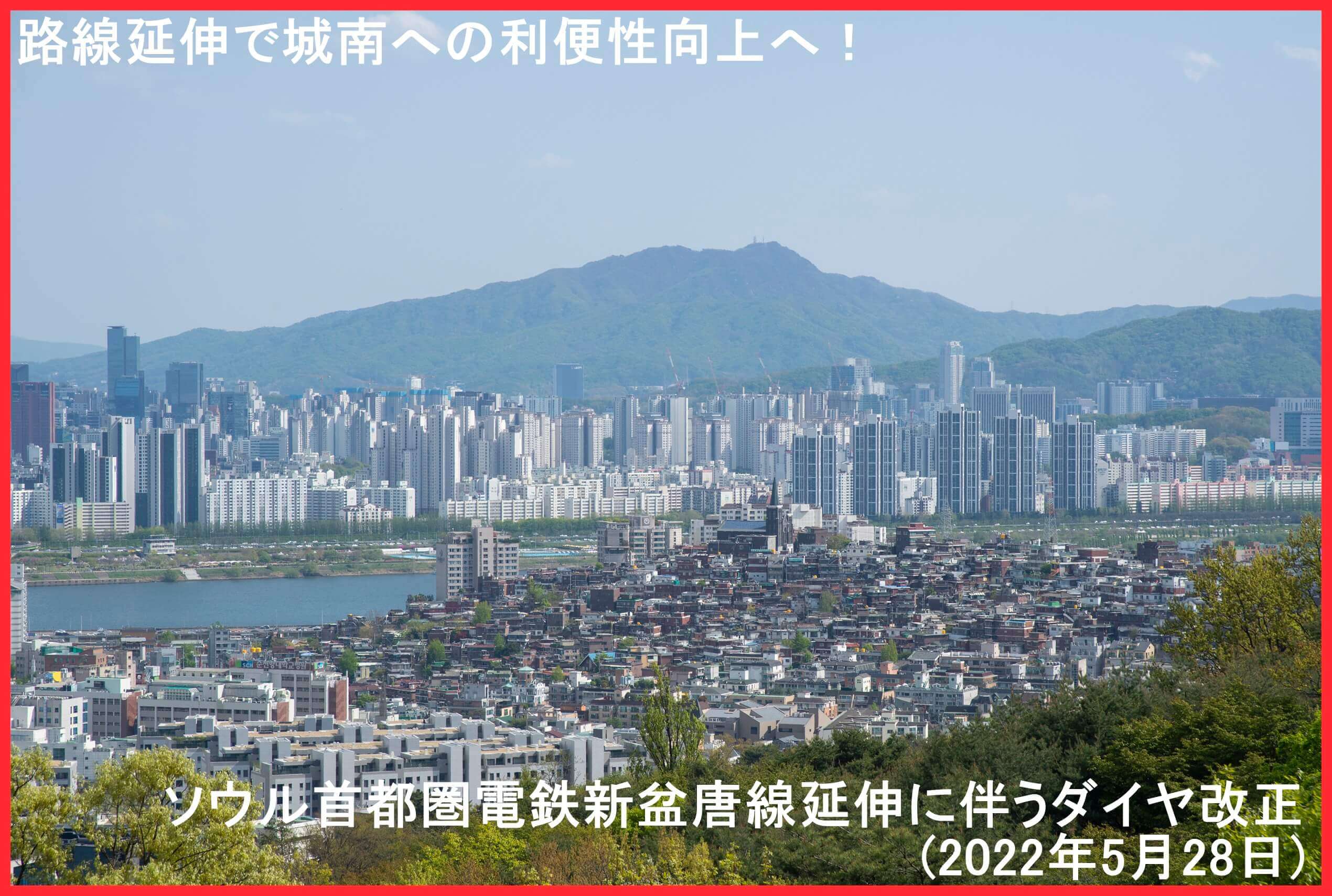

コメント